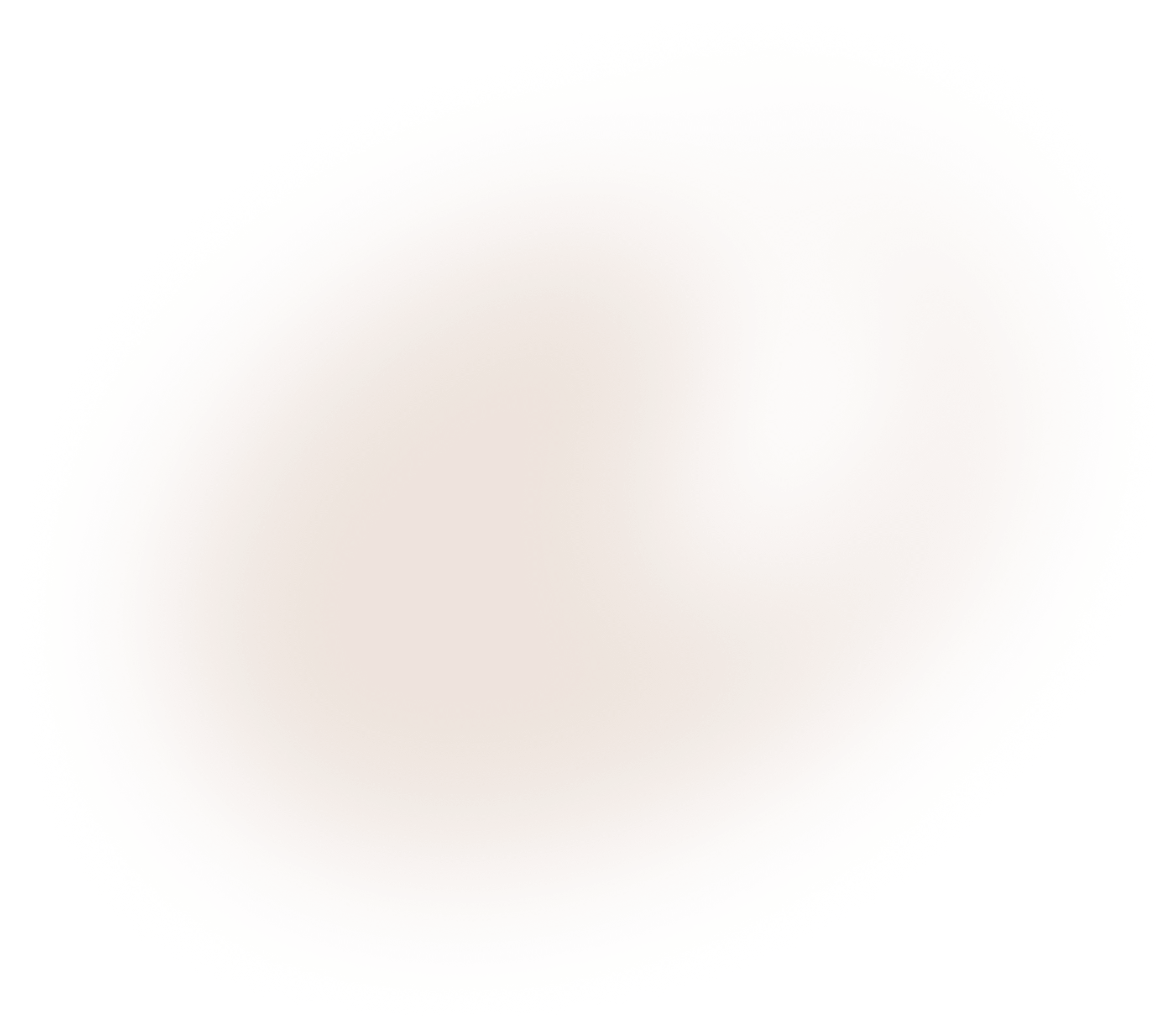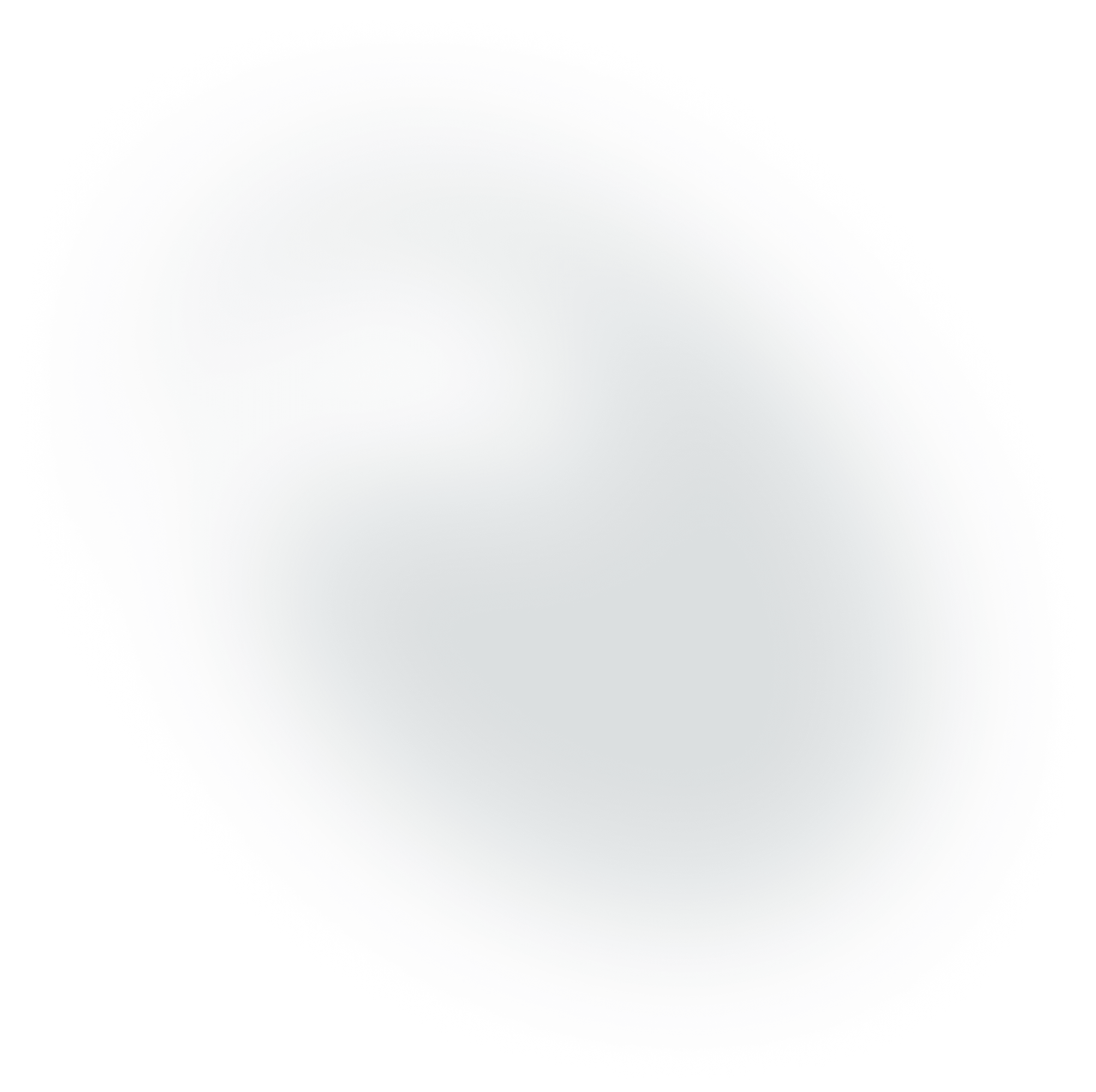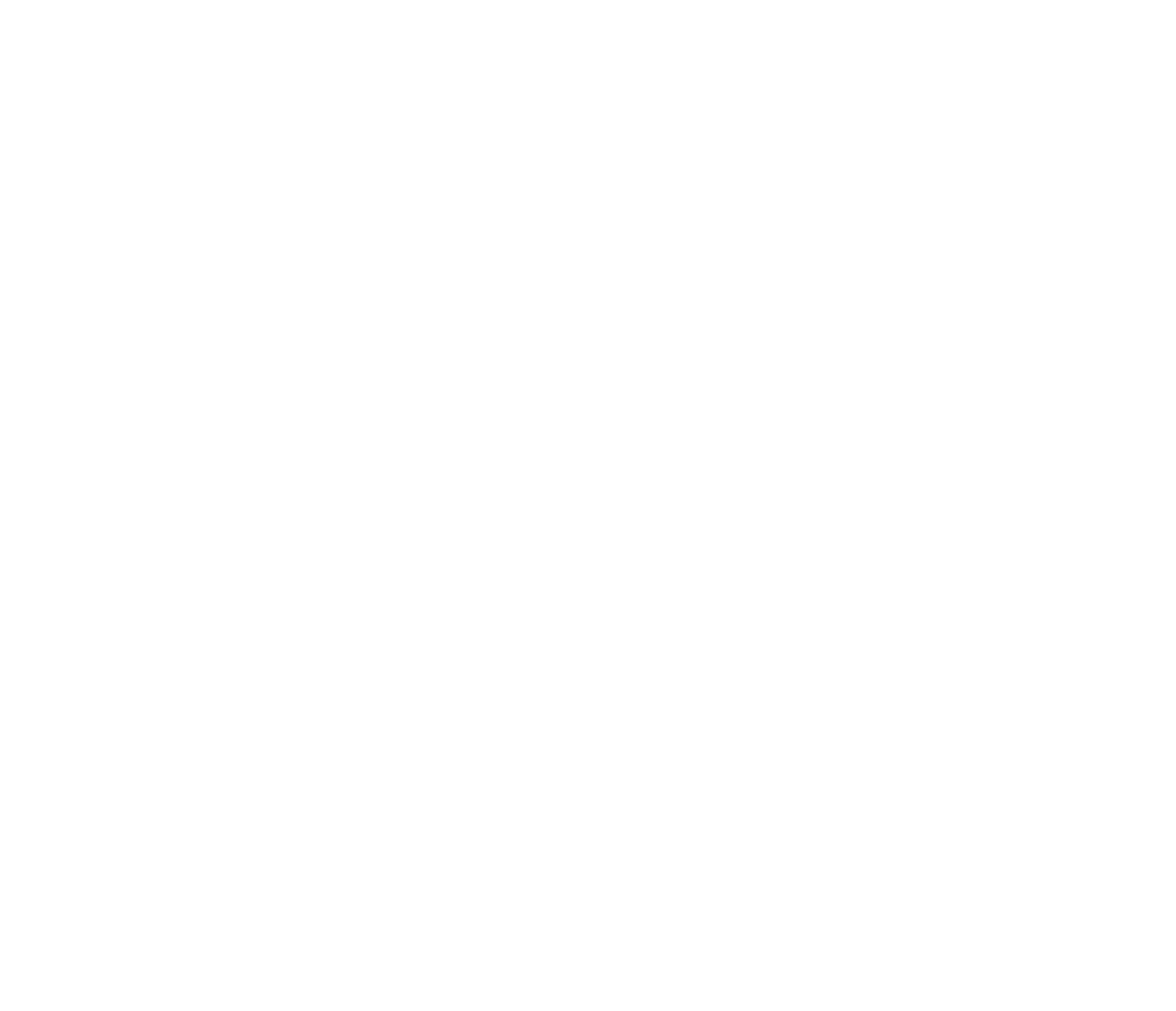新人採用担当スタッフにインタビュー!ピアスグループの魅力とは?
- アクセーヌ
- アナスタシア ミアレ
- アイブロウリスト
- ビューティカウンセラー
- #新卒採用
- #中途採用
- #ピアスグループを知る
- #キャリアチェンジ

美容師とアイリスト、どっちを目指す?メリットや働き方の違いを比較【求人情報あり】
- ケサランパサラン
- アナスタシア ミアレ
- インフェイシャス
- ビューズ
- アイデザイナー
- アイブロウリスト
- #職場環境
- #美容師

美容専門学校で学内ガイダンスを実施!美容師免許を活かすアイリストの仕事
- アナスタシア ミアレ
- アイブロウリスト
- #イベント
- #新卒採用
- #美容師

ピアスグループ施術ブランドの社内イベントを開催!美容学生さんたちの反応をレポート
- ケサランパサラン
- アナスタシア ミアレ
- インフェイシャス
- ビューズ
- アイデザイナー
- アイブロウリスト
- #イベント
- #新卒採用

美容部員は未経験でも転職可能!化粧品が好きな人におすすめできる理由
- カバーマーク
- アクセーヌ
- パウダーパレット
- ビューティカウンセラー
- #未経験
- #中途採用
- #職場環境
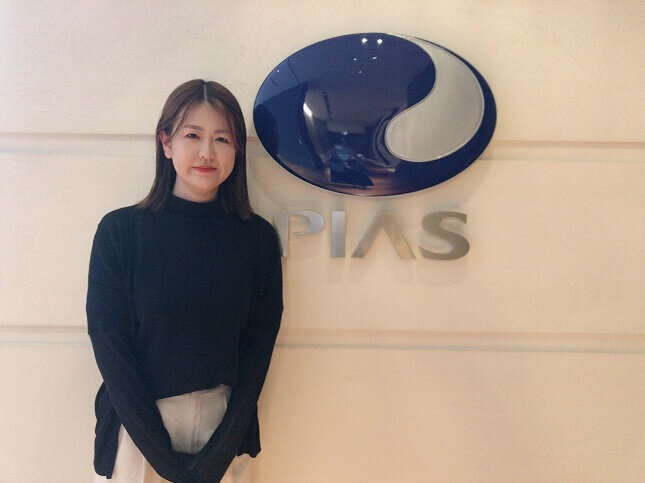
【採用担当が語る】ピアスグループにはキャリアチェンジのチャンスがある
- ケサランパサラン
- アイデザイナー
- アイブロウリスト
- #ピアスグループを知る
- #ハッピーリターン
- #キャリアチェンジ

ピアスグループが求める人物像、一緒に働きたいと思うスタッフの特徴を採用担当がお答えします!
- カバーマーク
- アクセーヌ
- パウダーパレット
- セルレ
- ビューティカウンセラー
- コスメティックアドバイザー
- #新卒採用
- #ピアスグループを知る

仕事のやりがいとは?ピアスグループを志望する方の疑問を解消
- カバーマーク
- アクセーヌ
- パウダーパレット
- ビューティカウンセラー
- #職場環境
- #仕事紹介
- #ピアスグループを知る

【塗るつけまつげ】【ハトムギ化粧水】などのコスメも、実はピアスグループの製品なんです!
- カバーマーク
- アクセーヌ
- ビューティカウンセラー
- #ピアスグループを知る

【美容部員を目指す方へ】ピアスグループが考える、想いが伝わる志望動機とは
- カバーマーク
- アクセーヌ
- パウダーパレット
- ビューティカウンセラー
- #新卒採用
- #ピアスグループを知る